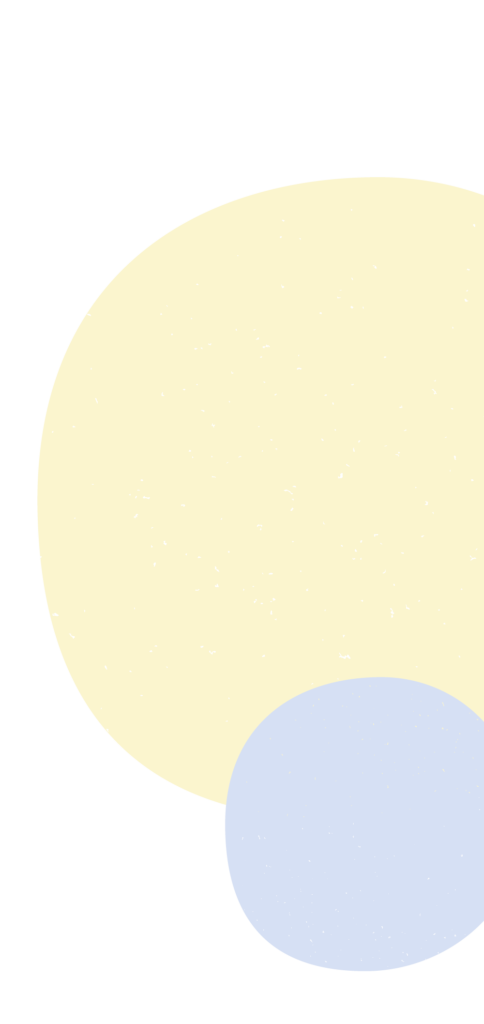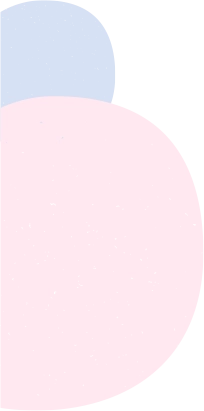看護師の定年とは何歳?
60歳からの働き方や
定年後の再就職も紹介
看護師として長年現場を支えてきた方の中には「定年後もこれまでの経験を活かして働きたい」と
考える方も少なくありません。近年は、再雇用制度や定年延長制度の導入が進み、
60歳を過ぎても活躍する看護師が増えています。とはいえ、勤務形態や給与水準など、
定年前とは異なる条件も多いため、事前に情報を整理しておくことが大切です。
この記事では、看護師の定年制度の概要や60歳からの働き方、
再就職先の選択肢までをわかりやすく解説します。

看護師の定年は何歳?
看護師の定年は、多くの病院や医療施設で「60歳」と定められています。これは一般企業と同様に、高年齢者雇用安定法の基準に基づくものです。特に、公立病院や自治体が運営する医療機関では、公務員規定に準じて定年が60歳とされており、全国的に見てもこの年齢が標準的といえるでしょう。一方で、少子高齢化の進行により、医療や介護の現場では人材不足が深刻化しています。定年を65歳に引き上げる、あるいは定年制度そのものを見直すなど、雇用継続を前提とした動きも見られるようになりました。長年にわたり培ってきた知識や技術を持つ看護師は、現場において欠かせない存在です。今後は、年齢にとらわれず活躍できる環境づくりが、医療機関にとってますます重要になるでしょう。
定年後も看護師として働ける?
看護師は、定年を迎えた後も働き続けることが可能です。現在では、高年齢者の就業機会を確保するための制度が整いつつあり、多くの医療機関で再雇用や勤務延長の仕組みが導入されています。ここでは、定年後も看護師として働ける背景や制度の仕組みについて解説します。
・ 65歳までの継続雇用は義務付けられている
・ 70歳までの雇用継続は努力義務で広がりつつある
・ シニア看護師の需要が高い職場もある
・ プラチナナースの活躍推進の動き
●65歳までの継続雇用は義務付けられている
高年齢者雇用安定法により、すべての事業主には65歳までの雇用確保が義務付けられています。医療機関や介護施設では「定年の引き上げ」「定年制の廃止」「再雇用制度や勤務延長制度の導入」など、いずれかの措置を講じる必要があります。実際、多くの病院や施設では再雇用制度を整備しており、希望すれば定年後も引き続き看護師として勤務できる体制が整いつつあります。長年勤めた職場でそのまま働けることで、新しい環境に慣れる負担を減らせるメリットもあります。一方で、再雇用後は給与水準が下がったり、勤務日数や業務内容が制限されたりするケースも少なくありません。再雇用の際は、契約内容を事前に確認し、無理のない働き方を選ぶことが、長く続けるためのポイントといえるでしょう。
参考:厚生労働省「高年齢者雇用安定法の概要」
参考:厚生労働省「55歳以上の看護師等の就業促進に係る好事例収集事業」
●70歳までの雇用継続は努力義務で広がりつつある
70歳までの就業機会確保は、現段階では「努力義務」とされています。この中には「定年を70歳に引き上げる」「70歳までの継続雇用」など、複数の形態が含まれます。法的義務ではないものの、医療・介護分野では深刻な人材不足を背景に、70歳まで働ける仕組みを導入する職場が増えています。こうした取り組みにより、経験豊富な看護師が希望に応じて柔軟な働き方を選べる環境が整いつつある点は、大きな利点といえるでしょう。特に、嘱託契約や短時間勤務などの活用は、身体的な負担を抑えながら専門性を発揮できる働き方として広がっています。
参考:厚生労働省「高年齢者雇用安定法の概要」
参考:厚生労働省「55歳以上の看護師等の就業促進に係る好事例収集事業」
●シニア看護師の需要が高い職場もある
高齢化が進む中で、医療・介護の現場では慢性的な人材不足が課題となっています。こうした状況を背景に、経験豊富なシニア看護師への需要は年々高まっており、60歳以降も現場で活躍する方が増えています。特に、訪問看護ステーションや介護施設では、落ち着いた対応力や豊富な臨床経験が評価されやすい傾向があります。また、後進の指導や新人教育など、人材育成面においても重要な役割を担う機会が増えています。一方で、夜勤やフルタイム勤務など、体力的な負担が大きい職場では、シニア看護師の働き方の調整が欠かせません。勤務日数や担当業務の見直しなど、無理のない形で長く続けられる環境を整えることが、定年後も安心して働き続けられるポイントといえるでしょう。
参考:日本看護協会「2021 年 看護職員実態調査」
●プラチナナースの活躍推進の動き
日本看護協会では、定年後の看護師がこれまでのキャリアを活かして働き続けられるよう、「プラチナナース」制度を推進しています。プラチナナースの活躍促進は、60歳以上の看護師を対象に、再就職支援や研修、就業相談などを行う仕組みで、定年後も安心して現場に戻れるようサポートするものです。求人紹介だけでなく、ブランクがある方を対象とした実技研修やキャリア相談の体制も充実しており、復職に不安を抱く方を幅広く支援しているのが特徴です。プラチナナース制度を活用することで、年齢を重ねても「看護師として社会に貢献し続けられる」という安心感とやりがいを得られる点が、大きな魅力といえるでしょう。
参考:日本看護協会「プラチナナース活躍推進BOOK」
定年後における60歳からの看護師の働き方
定年を迎えた後も看護師として働きたい場合、主に次の2つの選択肢があります。
1. 別の職場へ転職する
2. 今の職場で再雇用してもらう
別の職場へ転職する場合は、勤務時間や勤務地などの希望条件を重視して環境を選び直せる点が大きな魅力です。これまでの経験を活かしながら、訪問看護ステーションや介護施設、健診センターなど、体力的な負担が少ない職場へシフトする方も増えています。一方、現在の職場で再雇用を希望する場合は、慣れた環境で働き続けられる安心感があります。ただし、再雇用後はパートや契約社員としての勤務形態になるケースが多く、給与が下がることも考えられるでしょう。どちらの働き方を選ぶにしても、健康状態・生活環境・収入面のバランスを考慮し、無理のない働き方を選択することが大切です。
定年後も看護師として働くメリット
定年後も看護師として働き続けることは、経済的な安定だけでなく、長年の経験を社会に還元できるという意義もあります。
ここでは、定年後に働くことで得られる3つのメリットを紹介します。
1. 安定した収入を得られる
2. 長年培った経験を活かせる
3. やりがいやメリハリのある生活を過ごせる
●安定した収入を得られる
定年後の再就職や再雇用によって、年金や退職金に加え、安定した収入を確保できる点は大きな魅力です。近年の物価上昇や医療費の増加など、老後の生活費に不安を感じる人にとって、継続的な収入源は精神的な支えにもなります。また、パート勤務や短時間勤務など柔軟な働き方を選ぶことで、体への負担を抑えながら副収入を得られるのもメリットです。ただし、定年後も働き続ける場合は、収入に見合った勤務日数や業務負荷のバランスを見極めることも重要です。高齢になるほど、体調を崩すリスクも高くなるため、自分のペースを守りながら働く姿勢が長く続けるポイントとなるでしょう。
●長年培った経験を活かせる
60歳以降の看護師にとって、これまで培ってきた臨床経験は大きな強みです。経験に基づいた的確な判断や落ち着いた対応は、定年後であっても即戦力として高く評価されるでしょう。また、若手看護師の教育や指導を任されることも多く、後進の育成を通じて組織全体の質向上に貢献することもできます。専門分野のスキルを維持・発揮できる環境を選ぶことで「自分はまだ必要とされている」という実感を得られるのも、仕事を続ける上でのモチベーションとなるでしょう。
●やりがいやメリハリのある生活を過ごせる
仕事を続けて社会とのつながりを持ち続けることで、定年後もメリハリのある生活ができます。看護師は職業柄、人との関わりが多く、感謝の言葉を直接受け取る機会も多いでしょう。仕事を通して、働く喜びや存在意義を実感しやすいのは、看護師ならではのメリットでもあります。一方で、定年前と同様の働き方を続けると、体調を崩したり家庭との両立が難しくなったりするケースもあります。定年後も看護師として働く場合は「働く時間」と「プライベートの時間」のバランスを意識することが大切です。ライフスタイルを崩さずに現役を続けることで、仕事も私生活もより充実したものにできるでしょう。
看護師が定年後に働き続ける際の注意点
定年後も看護師として働くことには多くのメリットがありますが、体力面や収入面での課題も無視できません。
ここでは、定年後も働き続ける際に押さえておきたい注意点を紹介します。
1. 体力的な負担がある
2. 給与が減る可能性がある
●体力的な負担がある
看護師として60代以降も勤務する場合は、体力的な負担が大きくなりやすい点に注意が必要です。定年前と同様に夜勤やフルタイム勤務など重ねることで体調を崩し、長期的に働き続けることが難しくなるケースも少なくありません。現在、夜勤が多い職場に勤務している場合は、定年後の勤務体制について早めに職場へ相談しておくと安心です。たとえば「夜勤回数を減らす」「日勤専従に切り替える」「負担の少ない診療科へ異動する」など、調整の余地はあるでしょう。調整が難しい場合は、日勤中心のクリニックや健診センターなど、体力的な負担が少ない職場への転職を検討するのも現実的な選択肢です。自分の体力と生活リズムに合った働き方を見つけることが、定年後も無理なく働き続けるための第一歩となります。
●給与が減る可能性がある
定年後に再雇用される場合、正規雇用からパート勤務などへ切り替わる医療機関が多く、給与水準が下がるケースが一般的です。夜勤手当や役職手当がなくなることで、収入が大きく減少し、生活費や老後資金計画に影響する可能性もあります。収入減を補いたい場合は、非常勤勤務を組み合わせたり、訪問看護や介護施設など比較的報酬水準の高い職場を選んだりするのも一つの方法です。退職金や年金とのバランスを考慮しながら家計を見直すことで、安定した生活と働き方を両立しやすくなるでしょう。
定年後の看護師におすすめの転職先
看護師の定年後は、家庭との両立や体力面を考慮しながら、無理のない働き方を選ぶことが大切です。
ここでは、長年の経験を活かしつつ、安定して働きやすい6つの転職先を紹介します。
・ クリニック
・ 訪問看護ステーション
・ 介護福祉施設
・ 健診センター
・ 保育園
・ ケアマネージャー
●クリニック
クリニックは外来業務が中心で夜勤がなく、勤務時間が安定しているのが特徴です。患者数が限られているため、一人ひとりに丁寧な対応ができ、落ち着いた環境で働けます。パートや非常勤として働く看護師も多く、ライフスタイルに合わせて働ける職場といえるでしょう。また、少人数体制のクリニックでは、受付対応や事務作業など看護業務以外のサポートを求められることもあります。幅広い業務に柔軟に対応できる方や、コミュニケーションを大切にできる方に向いている職場といえます。一方で、給与水準は病院勤務よりもやや低い傾向があります。勤務時間や残業の有無、業務範囲などもクリニックによって大きく異なるため、応募前に確認しておくと安心です。
●訪問看護ステーション
在宅医療の需要拡大により、近年、訪問看護ステーションは全国的に増加しています。訪問看護の主な業務は、患者の病状観察や療養指導などが中心です。日勤のみの現場も多く、患者と家族に深く関われる点が魅力です。
一方で、移動や単独訪問が多く、最初のうちは心理的な負担を感じることもあるでしょう。気になる場合は、訪問件数や移動距離、サポート体制などを事前に確認しておくと安心です。体力や生活リズムに合う働き方を選ぶことが大切です。仲間と協力しながら働くよりも、臨床経験を活かして自立的に判断・行動したい方におすすめの働き方といえるでしょう。
参考:厚生労働省『在宅における訪問看護の役割』
参考:一般社団法人全国訪問看護事業協会
「令和6年度 訪問看護ステーション数 調査結果」
●介護福祉施設
高齢化が進む中で、介護福祉施設は看護師の需要が高い分野のひとつです。主な業務は、入居者の健康管理やバイタルチェック、服薬管理、医療機関との連携などです。デイサービスなど通所介護を行う施設であれば、夜勤がなく残業も少ないケースが多く、安定した勤務も可能でしょう。病院に比べて急変対応が少ないため、落ち着いた環境で長く働きたい方に適した職場といえます。ただし、医療行為よりも介護職員との連携が中心となるため、チームワークを重視した働き方が求められます。人間関係や連携の取りやすさを重視する方は、人員体制や看護師の配置数を事前に確認しておくと安心です。
●健診センター
健診センターは、採血や身体測定などルーティンワークが中心で、基本的に夜勤がありません。予約制を採用している施設も多く、残業が少ないのも特徴です。検査業務が中心のため、業務内容は比較的安定しており、身体介助などの力仕事もほとんどありません。勤務時間が規則的なため、生活リズムを整えたい方や、身体への負担を抑えながら働きたい看護師に適した職場といえるでしょう。ただし、繁忙期には受診者数が増加し、一時的に業務量が増える場合もあります。応募時には、1日の健診件数や採血担当範囲などを確認しておくと安心です。
●保育園
保育園で働く看護師の主な業務は、園児の健康管理や応急処置、感染症予防などです。子どもと触れ合う機会が多く、明るく穏やかな環境の中で働けるのが魅力です。ケガや体調不良時の応急処置やアレルギー対応、保育士や保護者への保健指導などを通じて、子どもたちの成長を長期的に見守れるのもやりがいのひとつでしょう。一方で、保育士や保護者との連携も欠かせないため、医療現場とは異なるコミュニケーション力が求められます。園児が体調を崩しやすい時期には対応が重なることもあるため、自身の体調管理やスケジュール調整力も欠かせません。応募前には、園児数や看護師の配置人数、医療連携体制を確認しておくとよいでしょう。
●ケアマネージャー
介護支援専門員(ケアマネージャー)は、看護師の経験を活かして医療と福祉をつなぐ役割を担う職種です。利用者一人ひとりの生活状況を踏まえ、最適な介護計画を立てるのが主な業務です。資格取得後はデスクワークが中心となり、身体的な負担が少ないのも特徴です。パート勤務や時短勤務など柔軟な働き方も可能で、長く安定して働きたい方にも向いています。さらに、資格手当が支給されるケースも多く、安定した収入を得やすい点も魅力です。資格を取得するには一定の実務経験と試験合格が必要なため、定年前から学習計画を立てておくとスムーズなキャリア転換につながるでしょう。
定年を迎えた看護師の再就職を成功に導くポイント
定年後も看護師として活躍し続けるには、再就職に向けた計画的な準備と日頃の意識づけが欠かせません。ここでは、再就職をスムーズに進めるために押さえておきたい5つのポイントを紹介します。
1. 人脈を形成しておく
2. 定年前からのキャリア設計をする
3. 体力づくりと健康管理をする
4. 複数の情報源を活用して選択肢を広げる
5. 就職支援制度を活用する
●人脈を形成しておく
定年後の再就職では、知人や元同僚などからの紹介で仕事が見つかるケースも多くみられます。医療・介護業界では慢性的な人材不足が続いており、信頼と実績のある知人の看護師に声がかかることも少なくありません。定年前から同僚や上司、他施設のスタッフなどとのつながりを意識的に広げておくことで、地域の求人情報や復職の機会を得やすくなるでしょう。学会や地域の勉強会、ナースセンター主催のセミナーなどにはこまめに顔を出しておくのがおすすめです。顔が知られているだけでも、有効な情報を得るチャンスが広がることがあるでしょう。
●定年前からのキャリア設計をする
「定年後はどのように働きたいか」を明確にしておくことで、再就職の選択肢は大きく広がります。たとえば、体力的に長時間勤務が難しい場合は、50代のうちに日勤中心の職場へシフトしておくのも一つの方法です。また、訪問看護や介護分野への転身を視野に入れる場合は、早めに関連資格の勉強を始めておくとスムーズなキャリアチェンジにつながります。現役のうちから定年後のキャリアを意識し、段階的に準備を進めておくことで、60歳以降も迷わず新しい一歩を踏み出せるでしょう。
●体力づくりと健康管理をする
定年後も看護師として働き続けるには、健康であることが前提です。夜勤や勤務時間が減っても、立ち仕事や移動の多い業務は変わらないため、一定の体力が求められます。年齢に関係なく、日頃からウォーキングやストレッチなど、身体を動かす習慣をつけておくとよいでしょう。また、定期的な健康診断を受け、持病や不調を早めにケアする意識も欠かせません。体調を整えておくことで仕事のパフォーマンスも安定し、生活全体の充実にもつながります。健康な体を保つことが、「長く働き続ける力」になるでしょう。
●複数の情報源を活用して選択肢を広げる
定年後の再就職を成功させるには、情報源を一つに絞らず、幅広い活用が大切です。看護師専門の求人サイトやシニア向け求人特集、ハローワーク、自治体のナースセンターなど、媒体によって得意な分野や掲載内容が異なります。看護師専門の転職サイトでは、キャリアアドバイザーを通じて非公開求人や最新の雇用動向を入手できます。一方、各自治体が運営するナースセンターでは、地域に密着した転職支援が受けられます。なかには看護師資格を持つ担当者に就職相談できる自治体もあり、幅広い支援制度が整っているのが特徴です。複数の情報源を組み合わせて活用することで、希望に合った働き方を見つけやすくなり、転職後のミスマッチを防ぐことにもつながります。
●就職支援制度を活用する
各自治体のナースセンターでは、定年後も働きたい看護師を対象にした就職支援制度を設けています。訪問看護や介護施設など、60歳以降の看護師を歓迎する求人も多く、求人紹介に加えて就職相談やキャリア面談を通じた個別支援も行われています。再就職に不安がある方は、復職支援の研修や講座を受講することで、知識やスキルを補い自信を持って再スタートできるでしょう。また、こうした研修の場では同じ立場の仲間と出会う機会も多く、情報交換や励まし合いがモチベーションの維持にもつながります。制度を活用することで、年齢にとらわれず、安心してキャリアを継続できる環境を整えられるでしょう。
定年後60代からの看護師求人例
近年では、病棟勤務に限らず、訪問看護ステーションや介護福祉施設などでも60歳以上の看護師を必要とする職場が増えています。
いずれも、これまでの経験を活かしながら無理なく働ける環境が整っており、日勤中心・短時間勤務・柔軟なシフトなど、ライフスタイルに合わせた働き方が可能です。人気の職場は早期に募集が終了するケースもあるため、気になる求人があれば早めに確認・応募すると良いでしょう。ここでは、60歳以上の看護師歓迎の求人例を2件ご紹介します。
<病棟・外来看護の求人例>
この求人は、500床以上の大規模病院における病棟・外来看護の非常勤募集です。時給1,400〜1,500円と安定しており、再雇用後も専門性を発揮しながら働きたい方に適しています。勤務は3交代制(変則を含む)のため、体力面を考慮しながら勤務時間やシフト希望を事前に確認しておくと安心です。契約は1年ごとの更新制で、勤務態度・業務評価・病院の経営状況などを踏まえて継続雇用の可能性があります。評価基準や更新条件は職場によって異なるため、長期的な勤務を希望する場合は事前に確認しておくとよいでしょう。
<訪問看護の求人例>
こちらは、訪問看護ステーションでの常勤(正規雇用)求人です。年間休日124日・有給休暇消化推奨など、ワークライフバランスを重視した働き方が可能な職場です。また、育児や介護との両立にも理解があるうえ、ブランクのある方や訪問看護未経験者もマンツーマンでサポートを受けられる体制が整っています。体力的に無理のない働き方を希望する方や、地域医療に関わりながら長く働きたい方におすすめです。
定年後も看護師として働くなら愛媛県ナースセンター
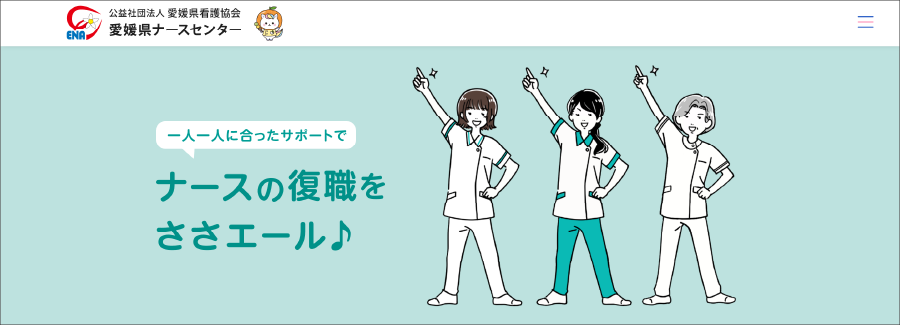
これまでの経験を活かして、定年後も看護師として働き続けたい方は、愛媛県ナースセンターの支援制度の活用がおすすめです。
愛媛県ナースセンターでは、看護師資格を持つ専任スタッフが、定年後の転職や再就職を丁寧にサポートしています。
主な支援内容は以下のとおりです。
・ 無料求人紹介
・ 就職相談
・ 講習会・セミナー
・ 実技研修
県内の病院・介護施設・訪問看護ステーションなど、地域に根ざした求人を多数取り扱っており、60歳以降の看護師を歓迎する求人も多数扱っています。就職相談では、働き方の希望や体力面の不安などに応じて、看護師資格を持つ専任スタッフが現場目線でアドバイスしています。また、講習会や実技研修を通じて、ブランクがある方でも自信を持って現場復帰できる体制を整えています。2025年8月からは、オンライン相談も開始し、自宅にいながらサポートが受けられるのも魅力です。まずは、以下の「e-ナースセンター」にて、無料で最新の求人情報の確認や個別相談など、充実したサポートを受けてみてください。
愛媛県看護協会「e-ナースセンター」の無料登録はこちら
まとめ
看護師は定年を迎えても活躍できる!
60歳からの働き方も自分らしくキャリアを築こう
看護師の定年は一般的に60歳ですが、再雇用制度を活用すれば65歳まで、職場によっては70歳まで働き続けることも可能です。医療・介護の現場では人材不足が続いており、経験豊富なシニア看護師の存在価値は今後さらに高まるでしょう。長年培った知識や技術を社会に還元できるのは、定年後だからこそ得られる大きなやりがいです。定年前からキャリア設計を意識して準備を進めておくことで、安心して第二のキャリアを築くことができるでしょう。「まだ現役でいたい」という想いを大切に、自分らしいペースで看護師としての道を歩み続けていきましょう。